競馬に興味を持ち始めると、レース後のニュースで「予後不良」という言葉を目にすることがあります。
しかし、競馬に詳しくない人にとっては、いったい何を意味するのか分かりづらいですよね。
この記事では、「予後不良」とは何か、なぜ起こるのか、そして競馬界でどのように向き合っているのかを、できるだけやさしく解説していきます。
今回はリバティアイランドをきっかけに執筆しました。「怪我しただけなのに、安楽死なんて・・・」と思われる方も多いと思います。この記事を読んで、馬が繊細な生き物であると共に、競走馬という職業(?)への敬意を持っていただければと思います。
予後不良とは?
「予後不良(よごふりょう)」とは、簡単にいうとケガや病気が重すぎて回復が見込めない状態を指します。
特に競走馬の場合は、回復が難しいと判断されたとき、人道的な観点から安楽死の措置が取られることを意味します。
つまり、競馬のレース中や調教中に重いケガを負った馬に対して、「もう元には戻れない」と診断され、その後、苦しみを和らげるために命を絶たれる――それが「予後不良」という言葉の背景にあるのです。
なぜ「予後不良」になるのか?
競走馬は、サラブレッドと呼ばれる非常にスピードに優れた品種です。
しかし、そのスピードを追求する過程で、身体が非常に繊細になっています。
特に負担がかかるのは脚(あし)です。
競馬では1トン近い負荷が脚にかかるとも言われ、レース中の激しい動きによって、骨折や靱帯の断裂といった重傷を負うことがあります。
人間であれば、骨折しても手術やリハビリで回復することが多いですが、馬は体の構造上、片足をかばうだけでも他の脚や内臓に負担がかかり、命に関わる合併症(蹄葉炎など)を引き起こしやすいのです。
そのため、競走馬の場合は「治すことがかえって苦しみを長引かせる」と判断されたとき、安楽死という選択肢が取られます。
「予後不良」という言葉の使われ方
レースの結果表や公式発表では、馬の負傷や安楽死措置についてストレートに書かれることはあまりありません。
代わりに、「予後不良」と表現されます。
これは、単なる隠語ではなく、
- 医学的なニュアンスを含んだ表現
- 関係者やファンへの配慮
として使われています。
レース後のニュースで「○○号は予後不良となりました」と発表された場合、それは「その馬が亡くなった」という非常に悲しい知らせだということになります。
馬たちへの敬意
競走馬たちは、私たちがレースで興奮したり感動したりする裏で、精一杯走り抜けています。
一生懸命に走るあまりケガを負ってしまうこともありますが、それは誰のせいでもありません。
関係者たちもできる限りケガを防ぐ努力をしており、万が一のときも馬にとって最も苦しまない道を選ぼうとしています。
また、近年では医学の進歩により、重いケガを負っても手術や治療で助かるケースも増えてきています。
それでも、すべての命を救うことは難しい現実もあるのです。
実際の例(有名馬の予後不良例)
競馬ファンにとっても、予後不良のニュースは非常にショックなものです。
ここでは、特に多くの人に衝撃を与えた有名馬たちの例を紹介します。
サイレンススズカ
1998年、天皇賞・秋に出走したサイレンススズカは、レース中に左前脚を骨折し、予後不良となりました。
スタート直後からハイペースで逃げ、数々のレコードを打ち立てた名馬だけに、その突然の別れに多くのファンが涙しました。
サイレンススズカの死は、レースにおけるリスクを改めて世間に知らしめる出来事となり、今も語り継がれています。
アグネスタキオン
2001年、皐月賞を制したアグネスタキオンも、脚部不安によって現役引退を余儀なくされました。
引退後は種牡馬として活躍しましたが、2009年に急性心不全で急死しています。
予後不良とは異なりますが、馬の生命がどれだけ繊細であるかを実感させるエピソードのひとつです。
キズナ(参考例:無事引退)
一方で、2015年に屈腱炎を発症したキズナは、無理に現役続行せず引退という道を選びました。
このように、近年は「無理をさせず引退させる」選択肢が増えてきたことも特筆すべき変化です。
安全対策の取り組み
競馬界では、馬たちの安全を守るためにさまざまな取り組みが行われています。
ここでは主なものを紹介します。
コースの改良
馬場(コース)のコンディションは、レースの安全性に大きく影響します。
最近では、ダートコースにクッション性の高い素材を使ったり、芝コースの水はけを改善するなどして、滑りにくく、ケガを防ぐ工夫が進められています。
また、レース当日の天候や馬場状態によって、距離短縮やレース中止の判断が行われることもあります。
獣医師の常駐と即時対応
すべての競馬場には、専門の獣医師が常駐しています。
レース中に異常が見られた場合はすぐに介入し、必要に応じてその場で治療を行う体制が整えられています。
これにより、ケガの程度が軽い場合は迅速な対応によって命が助かるケースも増えています。
訓練・調教の工夫
調教(トレーニング)段階でも、無理な負荷をかけすぎないよう、トレーナーたちは細心の注意を払っています。
筋肉や関節への負担を考慮したトレーニングメニューや、馬自身のコンディションを尊重した調整が行われています。
さらに、若い馬に対しては成長段階に合わせた丁寧な育成が重視されるようになり、長く健康に走れる馬づくりが進められています。
まとめ
- 「予後不良」は、馬が重いケガを負い回復の見込みがない場合にとられる措置です。
- サイレンススズカの例など、競馬ファンの心に深く刻まれた出来事もあります。
- 競馬界では、コース改良、獣医師の常駐、調教方法の見直しなど、安全対策が年々進化しています。
華やかなレースの裏には、馬たちの命と真剣に向き合う関係者たちの努力があります。
そして何より、ゴールを目指して懸命に走る馬たちへの感謝と敬意を忘れないことが、私たちファンにできる一番のことなのかもしれません。

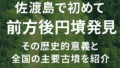

コメント